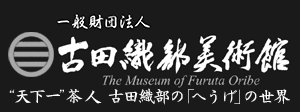当会の活動趣旨

古田織部(1543~1615)は諱(いみな)を重然(しげなり)といい、千利休亡き後、「天下一」と称された武将茶人です。
織部は、武名こそあまりないものの、茶の湯・連歌に秀で、信長横死後、太閤秀吉の御咄衆(御伽衆)となり、茶の湯の相談相手となります。その後、子の秀頼の他徳川家康に仕え、将軍家茶の湯指南役として将軍秀忠に直接茶の湯指導をしたことで知られています。織部は、利休の茶の湯を継承しつつ、茶道具・会席具の製作・建築・作庭など多岐にわたって独自の世界を開き、それらは「織部好み」と呼ばれました。慶長年間(1596~1615)に爆発的な流行をみせ、これは織部が亡くなった後の元和・寛永期(1615~1644)まで続きました。
当会は、織部好みの道具やその道具組、作法を研究して、織部が実際に行っていた点前に修正し、織部の精神までをも忠実に守り伝えることを目的とする組織です。会長を務める宮下玄覇は、京都市北山において一般財団法人古田織部美術館を運営し、啓蒙活動を行っております。
古田織部亡き後、その茶の湯は幕府や諸国の大名の茶堂を通じて伝えられていきました。現在では福岡藩の茶堂から豊後岡藩の家老家に伝わった織部流が知られています。
しかし、どこの流派についてもいえることですが、数百年、十数代も続くと、代々の家元の好みが反映され、流祖の点前とはかなり違ったものになっていきます。豊後織部流も例外ではありませんでした(岡﨑淵冲『点茶活法』)
時は平成となり、織部の茶会記や、幸いにして膨大に残る江戸時代前期の織部の茶書の翻刻が始まると、当会は織部の点前の修正作業を開始。その結果、400年ぶりに甦った織部の点前が、当会の点前です。
当会の活動により、織部の茶の湯がどのようなものであったのか、その実相に一歩でも迫り、またそれを一人でも多くの方に知っていただけますなら、これに勝る幸いはございません。
写真:織部肩衝耳付茶入・黒織部茶碗・美濃伊賀水指 / 青織部 重扇形 向付/ 向掛けした美濃伊賀花入
織部は、武名こそあまりないものの、茶の湯・連歌に秀で、信長横死後、太閤秀吉の御咄衆(御伽衆)となり、茶の湯の相談相手となります。その後、子の秀頼の他徳川家康に仕え、将軍家茶の湯指南役として将軍秀忠に直接茶の湯指導をしたことで知られています。織部は、利休の茶の湯を継承しつつ、茶道具・会席具の製作・建築・作庭など多岐にわたって独自の世界を開き、それらは「織部好み」と呼ばれました。慶長年間(1596~1615)に爆発的な流行をみせ、これは織部が亡くなった後の元和・寛永期(1615~1644)まで続きました。
当会は、織部好みの道具やその道具組、作法を研究して、織部が実際に行っていた点前に修正し、織部の精神までをも忠実に守り伝えることを目的とする組織です。会長を務める宮下玄覇は、京都市北山において一般財団法人古田織部美術館を運営し、啓蒙活動を行っております。
古田織部亡き後、その茶の湯は幕府や諸国の大名の茶堂を通じて伝えられていきました。現在では福岡藩の茶堂から豊後岡藩の家老家に伝わった織部流が知られています。
しかし、どこの流派についてもいえることですが、数百年、十数代も続くと、代々の家元の好みが反映され、流祖の点前とはかなり違ったものになっていきます。豊後織部流も例外ではありませんでした(岡﨑淵冲『点茶活法』)
時は平成となり、織部の茶会記や、幸いにして膨大に残る江戸時代前期の織部の茶書の翻刻が始まると、当会は織部の点前の修正作業を開始。その結果、400年ぶりに甦った織部の点前が、当会の点前です。
当会の活動により、織部の茶の湯がどのようなものであったのか、その実相に一歩でも迫り、またそれを一人でも多くの方に知っていただけますなら、これに勝る幸いはございません。
写真:織部肩衝耳付茶入・黒織部茶碗・美濃伊賀水指 / 青織部 重扇形 向付/ 向掛けした美濃伊賀花入
古田織部の主な門人
○武士
徳川秀忠 伊達政宗 佐竹義宣 毛利秀元 浅野幸長 金森可重(宗和の父)
島津義弘 小早川秀秋 大久保忠隣 桑山元晴 桑山貞晴(片桐石州の師)
大野治長 大野治房 小早川秀包 石川貞通 有馬豊氏 森忠政 石川康長 藤堂高虎
小堀遠州 上田宗箇 佐久間将監 加藤嘉明 竹中重利 板倉重宗 南部利直 永井尚政
○公家
広橋兼勝 近衛信尋 万里小路充房
○僧侶
教如(東本願寺法主) 妙法院宮 常胤法親王 安楽庵策伝 江月宗玩
○町衆
本阿弥光悦 角倉素庵 松屋久好
○武士
徳川秀忠 伊達政宗 佐竹義宣 毛利秀元 浅野幸長 金森可重(宗和の父)
島津義弘 小早川秀秋 大久保忠隣 桑山元晴 桑山貞晴(片桐石州の師)
大野治長 大野治房 小早川秀包 石川貞通 有馬豊氏 森忠政 石川康長 藤堂高虎
小堀遠州 上田宗箇 佐久間将監 加藤嘉明 竹中重利 板倉重宗 南部利直 永井尚政
○公家
広橋兼勝 近衛信尋 万里小路充房
○僧侶
教如(東本願寺法主) 妙法院宮 常胤法親王 安楽庵策伝 江月宗玩
○町衆
本阿弥光悦 角倉素庵 松屋久好
古田織部流の行事
| 1月上旬 土・日曜 | 東京・初釜 |
| 1月中~下旬 土・日曜 | 京都・初釜/御着甲始 (おきかぶとはじめ)(太閤山荘) |
| 2月 第2土曜 | 光悦忌(太閤山荘) |
| 2月 第4土曜 | 利休忌(太閤山荘) |
| 4月 第4土曜 | 武田信玄忌(太閤山荘) |
| 5月 第2土曜 | 初風炉 |
| 6月 第1土曜 | 東京織部忌茶会(立礼) |
| 6月中旬 土曜 | 流祖(織部)忌(太閤山荘) |
| 8月 第4土曜 | 太閤(秀吉)祭(神事)・茶会(太閤山荘) |
| 9月 第4土曜 | 織田道八(左門)忌(太閤山荘) ※有楽嫡男で傾奇者の第一人者 |
| 10月 土曜 | (公家)猪熊教利忌(太閤山荘) ※「天下無双」の美男子でファッションリーダー |
| 10月下旬 | 口切茶事 |
| 12月 第2土曜 | キリシタン茶会(右近祭)(太閤山荘) ※織部嫡男・重広や古田家中はほとんどがキリシタン(のちに棄教) |